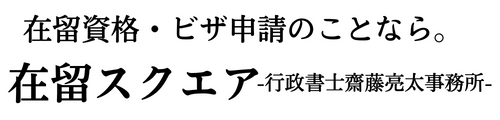就労ビザについて
在留資格は全部で29種類ありますが、そのうち就労系のビザは以下の通りです。
| 在留資格カテゴリー | 在留資格名 | 主な活動内容・対象者の例 |
| 専門的・技術的分野 | 教授 (Professor) | 大学や高等専門学校等での研究、研究の指導、教育活動(例:大学教授、准教授) |
| 芸術 (Artist) | 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動(例:作曲家、画家、作家、写真家) | |
| 宗教 (Religious Activities) | 外国の宗教団体から派遣された宗教家が行う布教等の宗教上の活動(例:僧侶、司教、牧師) | |
| 報道 (Journalist) | 外国の報道機関との契約に基づく取材等の報道活動(例:記者、カメラマン、編集者) | |
| 高度専門職 (Highly Skilled Professional) | ポイント制(学歴、職歴、年収等)で評価。高度な能力を持つ人材が行う活動(1号イ・ロ・ハ、2号)。優遇措置あり。 | |
| 経営・管理 (Business Manager) | 日本での事業の経営または管理に従事する活動(例:企業の社長、役員、管理者) | |
| 法律・会計業務 (Legal/Accounting Services) | 日本の法律・会計に関する資格(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等)に基づき行う法律・会計業務 | |
| 医療 (Medical Services) | 日本の医療に関する資格(医師、歯科医師、看護師、薬剤師等)に基づき行う医療活動 | |
| 研究 (Researcher) | 日本の公私の機関との契約に基づく研究活動(例:政府関係機関や民間企業等の研究者) | |
| 教育 (Instructor) | 日本の小・中・高校、専修学校等での語学教育その他の教育活動(例:語学教師) | |
| 技術・人文知識・国際業務 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services) | 自然科学・人文科学の知識や技術、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務(例:エンジニア、プログラマー、通訳、翻訳、デザイナー、マーケター、私企業の語学教師など) | |
| 企業内転勤 (Intra-company Transferee) | 外国の事業所からの転勤者で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う者 | |
| 介護 (Nursing care) | 日本の介護福祉士の資格に基づき、介護または介護の指導を行う業務 | |
| 興行 (Entertainer) | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動またはその他の芸能活動(例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手) | |
| 技能 (Skilled Labor) | 日本の公私の機関との契約に基づく、産業上の特殊な分野に属する熟練技能を要する業務(例:外国料理調理師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、貴金属加工職人など) | |
| 特定技能 | 特定技能1号 (Specified Skilled Worker (i)) | 特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事 |
| 特定技能2号 (Specified Skilled Worker (ii)) | 特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事(家族帯同可、在留期間更新上限なし) | |
| 技能実習 (育成就労へ移行予定) | 技能実習 (Technical Intern Training) | 日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転することを目的とする活動(実務を通じた習得) |
| 特定活動 | 特定活動 (Designated Activities) | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。就労が認められるものとして以下のような例がある。ワーキングホリデー・EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者・インターンシップ・デジタルノマド・製造業外国人材受入れ(要件あり) など |
就労関連の在留資格に共通する主なポイント
適切な在留資格の取得:
- 外国籍の方が日本で収入を伴う活動(就労)を行うには、原則として、その活動内容に応じた就労可能な在留資格を取得する必要があります。
活動内容の制限:
- 原則として、許可された在留資格で定められた範囲内の活動(職種・業務内容)しか行うことができません。
- 許可された範囲外の就労活動を行うことはできません(違反すると罰則や在留資格取消、退去強制の対象となり得ます)。
転職・活動内容変更時の注意:
- 転職などにより、従事する活動内容が現在の在留資格の範囲を超える場合や、所属機関が変わる場合には、事前に「在留資格変更許可申請」や「所属機関に関する届出」など、必要な手続きを入管に対して行う必要があります。
受入れ機関(雇用主等)の審査:
- 在留資格の申請(新規・変更・更新)においては、申請者本人だけでなく、受入れ機関(会社・雇用主)の事業の安定性・継続性、適正な雇用・労働条件なども審査の対象となる場合があります。
申請手続き:
- 新規に入国する場合は、多くの場合、日本国内の代理人(受入れ機関職員や行政書士など)が「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行い、証明書が交付された後、本人が在外日本公館で査証(ビザ)を取得して来日します。
- すでに日本に他の在留資格で滞在している場合は、現在何らかの在留資格を持って滞在していると思われますので「在留資格変更許可申請」を行います。
- 在留期間を延長する場合は、「在留期間更新許可申請」を行います。
日本の法令遵守義務:
- 入管法はもちろん、労働基準法、最低賃金法、税法、社会保険(年金・健康保険)関連法など、日本の法律・ルールを遵守する必要があります。
各種届出義務:
- 住居地を変更した場合や、所属機関(勤務先など)の名称・所在地変更、倒産、離職、移籍などがあった場合に、入管への届出が必要となることがあります。
在留期間の管理:
- 許可された在留期間には1年・3年・5年などの期限があり、更新しなければなりません。在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。本人が忘れてしまい不法滞在(オーバーステイ)とならないよう、期限の管理についても注意が必要です。