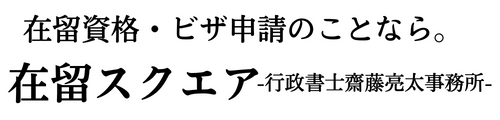【行政書士監修】子供と日本で暮らしたい!離婚後の「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更|必要書類と手続きを徹底解説
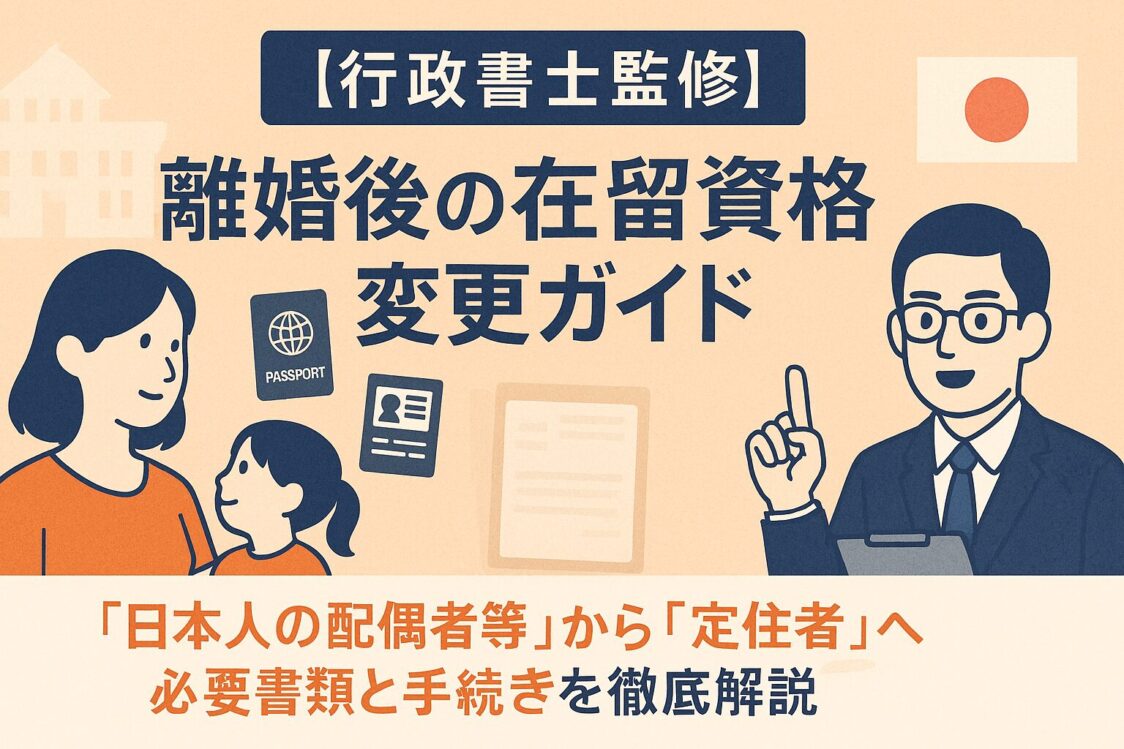
「日本人と離婚することになったけど、子供と一緒にこれからも日本で暮らしたい…」 「日本人の配偶者等のビザ(在留資格)はどうなっちゃうの?」 「自分で手続きできるか不安…どんな書類が必要なんだろう?」
日本人の方との離婚は、外国人の方にとって精神的な負担が大きいだけでなく、日本での生活基盤である「在留資格」にも大きな影響を与えます。特に、大切なお子様がいらっしゃる場合、その不安は計り知れないものでしょう。
ご安心ください。日本人の方と離婚した後でも、お子様と一緒に日本で暮らし続けるための道はあります。その代表的な方法が**「定住者」**という在留資格への変更です。
この記事では、在留資格申請を専門とする行政書士が、お子様がいる状況で日本人の方と離婚された(または、これからされる)外国人の方が、「日本人の配偶者等」から「定住者」へ在留資格を変更するための手続きや必要書類、そして許可を得るための重要なポイントについて、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
Check Point!
- 離婚後の「日本人の配偶者等」の在留資格の扱い
- なぜ「定住者」への変更が一般的なのか
- 「定住者」へ変更するための条件
- 具体的な手続きの流れと必要書類の詳細
- 申請にあたっての注意点やよくある質問
- 専門家(行政書士)に相談するメリット
ご自身での手続きに不安を感じている方、確実にお子様との日本での生活を守りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 離婚したら「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなる?
まず、大前提として知っておかなければならないことがあります。日本人の方との離婚が成立すると、「日本人の配偶者等」の在留資格は、原則としてその基盤を失うことになります。
1-1. 原則として在留資格は失効・取消しの対象に
「日本人の配偶者等」の在留資格は、あくまで「日本人の配偶者」という身分に基づいて許可されているものです。そのため、離婚によってその身分がなくなると、在留資格の前提条件を満たさなくなるのです。
具体的には、離婚後もそのままにしておくと、次回の在留期間更新申請が不許可になったり、場合によっては在留資格が取り消されたりする可能性があります。
- 参照: 出入国管理及び難民認定法 第22条の4(在留資格の取消し)
1-2. 離婚後14日以内の「届出義務」
日本人の方と離婚した場合、14日以内に出入国在留管理庁(入管)へその事実を届け出る義務があります。これは法律で定められており、怠ると罰金が科されたり、今後の在留資格申請に不利になったりする可能性があります。
届出は、お近くの地方出入国在留管理局の窓口、または郵送、インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)で行うことができます。
- 参照: 出入国在留管理庁:所属(活動)機関等に関する届出手続
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00002.html
- ※「配偶者に関する届出」の項目をご確認ください。
1-3. そのまま放置するリスクは大きい!
「届出だけすれば大丈夫?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。届出はあくまで離婚の事実を報告する義務であり、在留資格の問題が解決するわけではありません。
離婚後、正当な理由なく6ヶ月以上「日本人の配偶者等」としての活動(=夫婦としての同居・協力・扶助)を行わないで在留していると、在留資格取消しの対象となります。
つまり、離婚後は速やかに他の適切な在留資格への変更申請を行う必要があるのです。
2. 子供と一緒に日本で暮らすための選択肢:「定住者」ビザとは?
離婚後、お子様と一緒に日本で生活を続けるためには、在留資格を変更する必要があります。その最も有力な選択肢となるのが「定住者」ビザです。
2-1. なぜ「定住者」への変更が多いのか?
日本人との離婚後、未成年で扶養を受ける実子(あなたのお子様)を日本で監護・養育する場合、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性が高いからです。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格であり、離婚によって日本人の配偶者という身分を失ったものの、日本人の実子を養育するという人道的な配慮から認められるケースが多くあります。
2-2. 「定住者」ビザでできること・メリット
「定住者」の在留資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。
定住者のメリット
- 就労活動に制限がない: 原則として、職種や業種に制限なく働くことができます。(公序良俗に反する仕事を除く)
- 安定した在留: 在留期間は通常1年、3年、5年のいずれかで、更新も可能です。
- 永住許可申請への道: 一定期間「定住者」として在留し、要件を満たせば「永住者」への変更申請も可能になります。
- 社会保障: 日本人と同じように、健康保険や年金などの社会保障制度に加入できます。
お子様を育てながら安定した生活基盤を築く上で、「定住者」は非常に有利な在留資格と言えるでしょう。
- 参照: 出入国在留管理庁:在留資格「定住者」
2-3. 他の在留資格への変更可能性は?
もちろん、「定住者」以外への変更可能性もゼロではありません。
その他の在留資格
- 就労ビザ: ご自身の学歴や職務経歴が、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの要件を満たしていれば、そちらへの変更も考えられます。ただし、就労ビザは職種が限定されるため、仕事の選択肢は狭まります。
- 永住者: 離婚前にすでに永住許可の要件を満たしている場合は、永住許可申請を検討することも可能です。
- 日本人の実子としての永住許可: お子様が日本国籍の場合、その実親として永住許可申請の要件が緩和される可能性もありますが、ハードルは高い傾向にあります。
しかし、多くの場合、お子様を日本で養育するという状況においては、「定住者」への変更が最も現実的で一般的な選択肢となります。
3. 「定住者」ビザへの変更が認められるためのポイント
「定住者」への変更申請をすれば、必ず許可されるわけではありません。入管は、いくつかの重要なポイントを審査します。
3-1. 子供の親権・監護権を持っていること
「定住者」への変更が認められる大前提として、あなたが離婚後もお子様の親権者または監護権者であることが必要です。日本の法律では、未成年の子供には必ず親権者を定めることになっています。
- 親権: 子供の財産管理や法律行為の代理などを行う権利・義務
- 監護権: 子供と一緒に暮らし、身の回りの世話や教育を行う権利・義務
離婚協議の際に、必ず親権者(または監護権者)をあなたに指定するよう取り決めることが重要です。通常は、離婚届に親権者を記載します。もし、元配偶者が親権者となった場合でも、あなたが実際に子供を引き取って育てている(監護権がある)ことを客観的に証明できれば、認められる可能性はあります。
3-2. 日本で子供を養育していく意思と能力があること
申請者であるあなたが、今後もお子様を日本で責任を持って育てていく強い意思と、実際に養育できる能力(時間的、環境的側面も含む)があることを示す必要があります。
例えば、お子様の学校のこと、住環境、今後の教育方針などを具体的に説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。
3-3. 安定した収入・生計維持能力があること
お子様との生活を維持していくために、安定した収入があることは非常に重要な審査ポイントです。
- ご自身の収入: 正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態は問われませんが、継続的かつ安定した収入があることを証明する必要があります。具体的な収入額の基準は明示されていませんが、お住まいの地域の生活保護基準などが一つの目安とされることがあります。
- 元配偶者からの養育費: 離婚協議で養育費の取り決めをし、実際に支払いを受けている場合は、それも生計維持能力の一部として考慮されます。公正証書などで取り決めを文書化しておくと、証明力が高まります。
- 公的扶助: 生活保護などの公的扶助を受けている場合、許可のハードルは高くなる傾向にありますが、必ずしも不許可になるわけではありません。個別の事情を丁寧に説明する必要があります。
- 預貯金: 一定額の預貯金があることも、安定性の補強材料となります。
収入が不安定な場合や、離婚直後でまだ仕事が決まっていない場合などは、今後の就職活動の状況や具体的な収入見込みなどを説明する必要があります。
3-4. 身元保証人の必要性について
「定住者」への変更申請では、多くの場合、日本に居住する、安定した収入のある身元保証人を立てることが求められます。身元保証人は、あなたが日本で法令を遵守し、公的義務を履行し、経済的に困窮した場合に支援することを保証する役割を担います。
身元保証人は、元配偶者、ご自身の親族(日本在住の場合)、会社の同僚や上司、親しい友人などに依頼することが一般的です。ただし、誰でもなれるわけではなく、安定した収入があることなどが求められます。
身元保証人が見つからない場合でも、正直にその事情を説明し、他の方法(預貯金の証明など)で生計維持能力を立証することで、許可される可能性もあります。諦めずにご相談ください。
4. 【ステップ解説】「定住者」への在留資格変更手続きの流れ
ここでは、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更申請の一般的な流れを解説します。
4-1. ステップ1:必要書類の準備
後述する「必要書類リスト」を参考に、漏れなく書類を集めます。書類の中には、市区町村役場や法務局で取得するもの、勤務先に発行を依頼するものなど、入手までに時間がかかるものもありますので、早めに準備を始めましょう。
4-2. ステップ2:申請書の作成
出入国在留管理庁のウェブサイトから「在留資格変更許可申請書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。記入内容に誤りや矛盾がないよう、慎重に作成しましょう。申請理由書(別途作成)では、離婚に至った経緯、お子様の親権・監護状況、今後の日本での生活設計などを具体的に記述します。
- 参照: 出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請(申請書様式)
4-3. ステップ3:地方出入国在留管理局への申請
準備した書類一式を、あなたの住所地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局・出張所)の窓口に提出します。申請時には、パスポートと在留カードの提示が必要です。
4-4. ステップ4:審査期間と結果の通知
申請が受理されると審査が開始されます。標準的な審査期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされていますが、個別のケースによってはそれ以上かかることもあります。審査期間中に追加書類の提出や説明を求められることもあります。
審査が完了すると、結果がハガキ(または封書)で通知されます。
4-5. ステップ5:新しい在留カードの受領
許可の通知を受け取ったら、指定された期間内に、通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料納付書(収入印紙を貼付)を持って、申請した入管へ行き、新しい「定住者」の在留カードを受け取ります。これで手続きは完了です。
5. 【完全リスト】「定住者」への変更申請に必要な書類
必要書類は、申請者の方の個別の状況によって異なりますが、一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。最新の情報やご自身の状況に応じた詳細は、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。
(注:以下のリストは一般的なものであり、これ以外にも個別の事情に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。)
5-1. 全員共通で必要な書類
- 在留資格変更許可申請書: 1通(証明写真貼付)
- 写真(縦4cm×横3cm): 1葉(申請前3ヶ月以内に撮影、無帽、無背景、鮮明なもの)
- パスポート及び在留カード: 提示
- 申請人の日本における活動内容に応じた資料: (定住者の場合は通常、身分関係や生計維持能力に関する書類が中心となります)
5-2. 離婚の事実を証明する書類
- 日本人元配偶者の戸籍謄本: 1通(離婚の事実が記載されているもの)
- ※離婚届提出後、戸籍に記載されるまで時間がかかる場合があります。その場合は「離婚届受理証明書」を先に提出し、後日戸籍謄本を追加提出することもあります。
- 離婚届受理証明書: 1通(戸籍謄本に離婚の記載が間に合わない場合など)
5-3. 子供に関する書類
- お子様の出生届受理証明書または出生証明書の写し: 1通
- お子様の住民票: 1通(世帯全員の記載があり、マイナンバーが省略されているもの)
- ※お子様が日本国籍の場合は戸籍謄本も必要です。
5-4. 親権・監護権を証明する書類
- 日本人元配偶者の戸籍謄本: (上記5-2と兼用可。親権者の記載を確認)
- その他、監護権を証明する資料: (離婚協議書、調停調書、審判書、判決書の写しなど、親権者とは別に監護権者を定めている場合)
5-5. 生計維持能力を証明する書類
- 申請人(あなた)の職業及び収入に関する証明書:
- 在職証明書: 1通
- 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(年間総所得及び納税状況が記載されたもの): 直近1年分 各1通
- ※市区町村役場で取得します。取得できない場合は理由書や給与明細、源泉徴収票などで補足します。
- 預貯金通帳の写しまたは残高証明書: 適宜
- 養育費の取り決め及び支払い状況がわかる資料: (公正証書、合意書、振込記録のある通帳の写しなど)
5-6. 身元保証に関する書類
- 身元保証書: 1通(出入国在留管理庁指定の様式)
- 身元保証人の身分証明書: (運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- 身元保証人の職業及び収入に関する証明書: (上記5-5と同様の書類)
- 身元保証人の住民票: 1通(世帯全員の記載があり、マイナンバーが省略されているもの)
5-7. その他状況に応じて必要となる書類
- 理由書: なぜ「定住者」への変更が必要なのか、離婚の経緯、子供の養育状況、今後の生活設計などを具体的に説明する書類。書式は自由ですが、許可を得る上で非常に重要です。
- 住居に関する資料: (賃貸借契約書の写し、不動産登記事項証明書など)
- その他、入管が必要と認める書類: 審査の過程で追加提出を求められることがあります。
【書類準備のポイント】
- 最新のものを準備する: 証明書類は、通常、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
- 日本語訳を添付する: 外国語で作成された書類には、必ず日本語の翻訳文を添付してください。翻訳者の氏名と連絡先を記載する必要があります。
- コピーと原本: 提出する書類(コピー可のもの)と、窓口で提示する原本(パスポート、在留カードなど)を区別して準備しましょう。
6. 申請前に確認!よくある質問(FAQ)と注意点
在留資格変更申請にあたっては、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、よくある質問と注意点について解説します。
6-1. Q. 離婚協議中でも申請できる?

現在離婚協議中なのですが今から先に申請できますか?
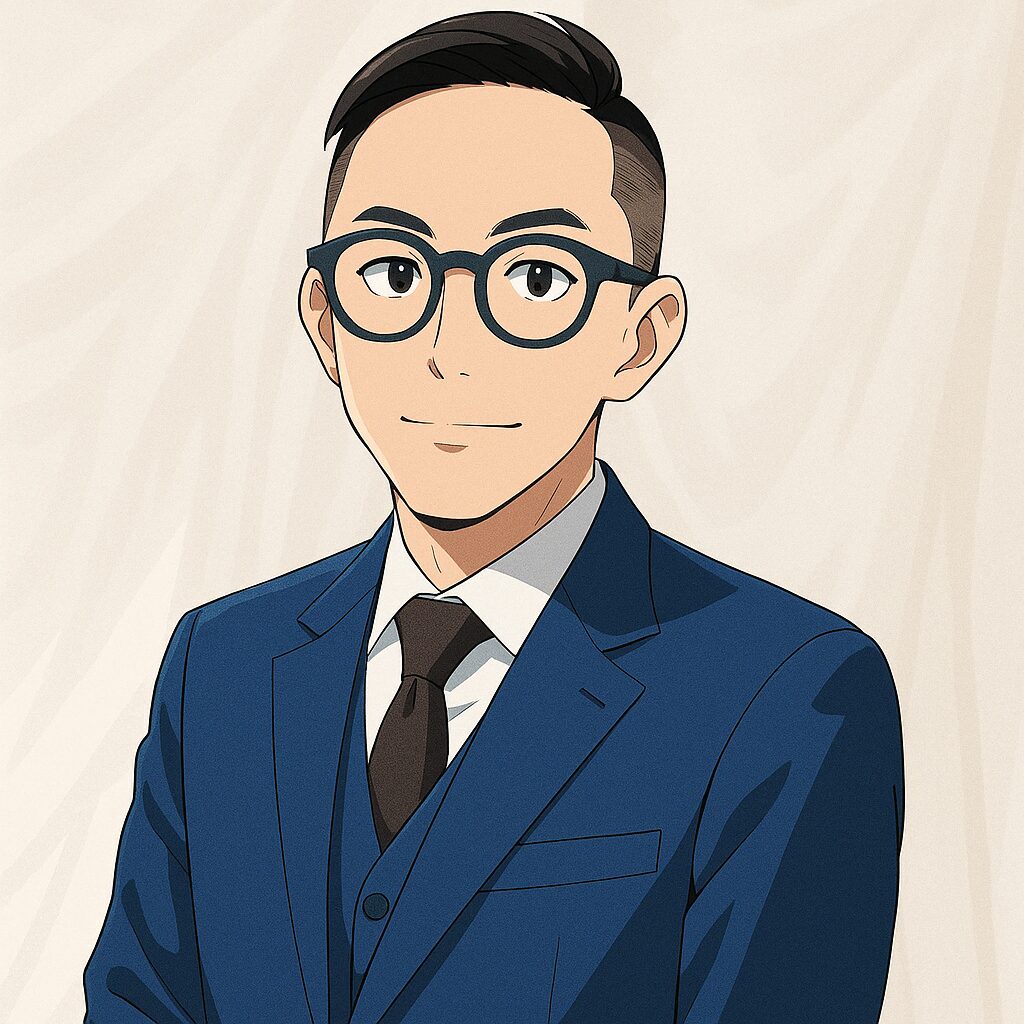
離婚が成立していない(離婚届が受理されていない)段階では、原則として「定住者」への変更申請はできません。ただし、離婚調停中であるなど離婚が確実に見込まれる状況であれば、事前に相談等の準備はしておいた方が良いでしょう。
6-2. Q. 収入が不安定でも許可される?

収入が不安定でも許可されますか?
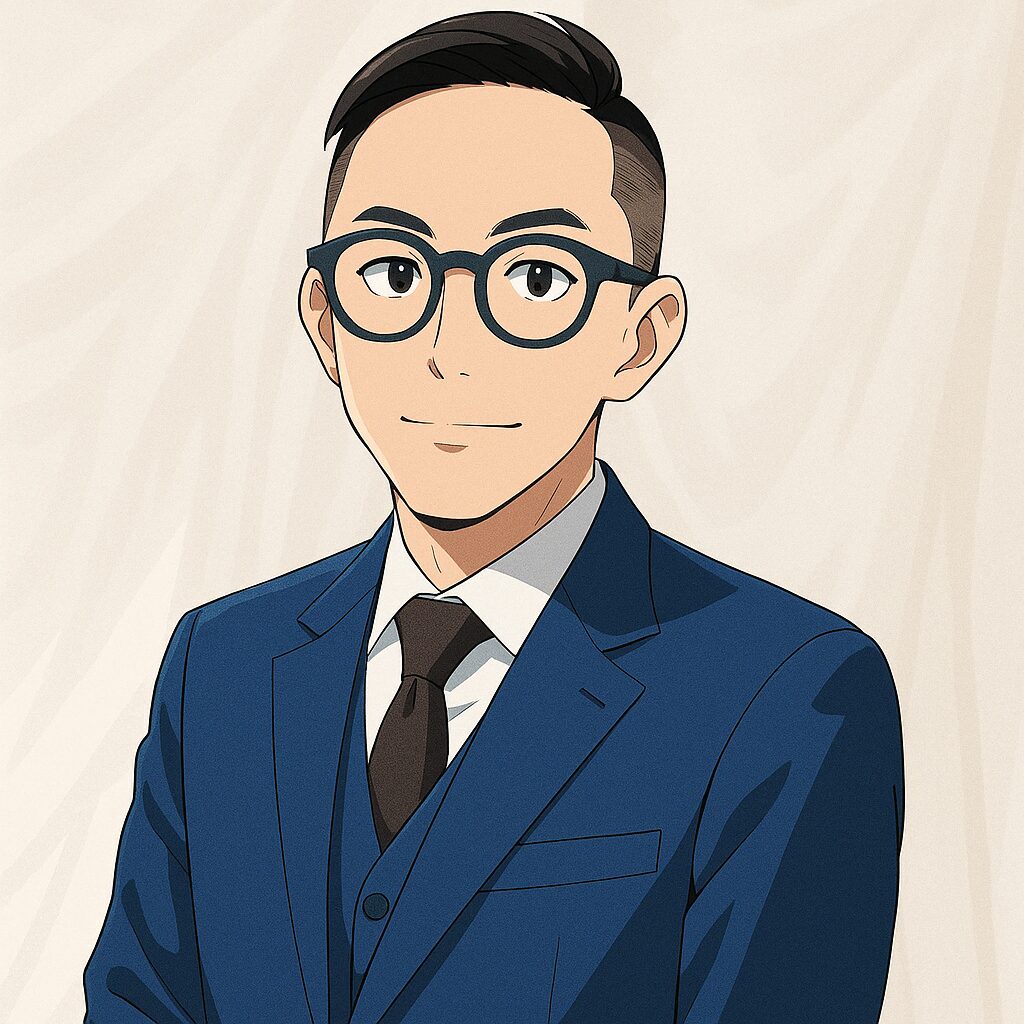
収入の安定性は重要な審査ポイントですが、一時的に不安定であっても、今後の安定した収入の見込み(就職内定など)や、十分な預貯金、養育費の受給実績などを具体的に示すことができれば、許可される可能性はあります。正直に状況を説明し、生計維持能力を補強する資料をできる限り提出することが大切です。
6-3. Q. 身元保証人が見つからない場合は?

身元保証人がいません。見つからない場合はどうすればいいですか?
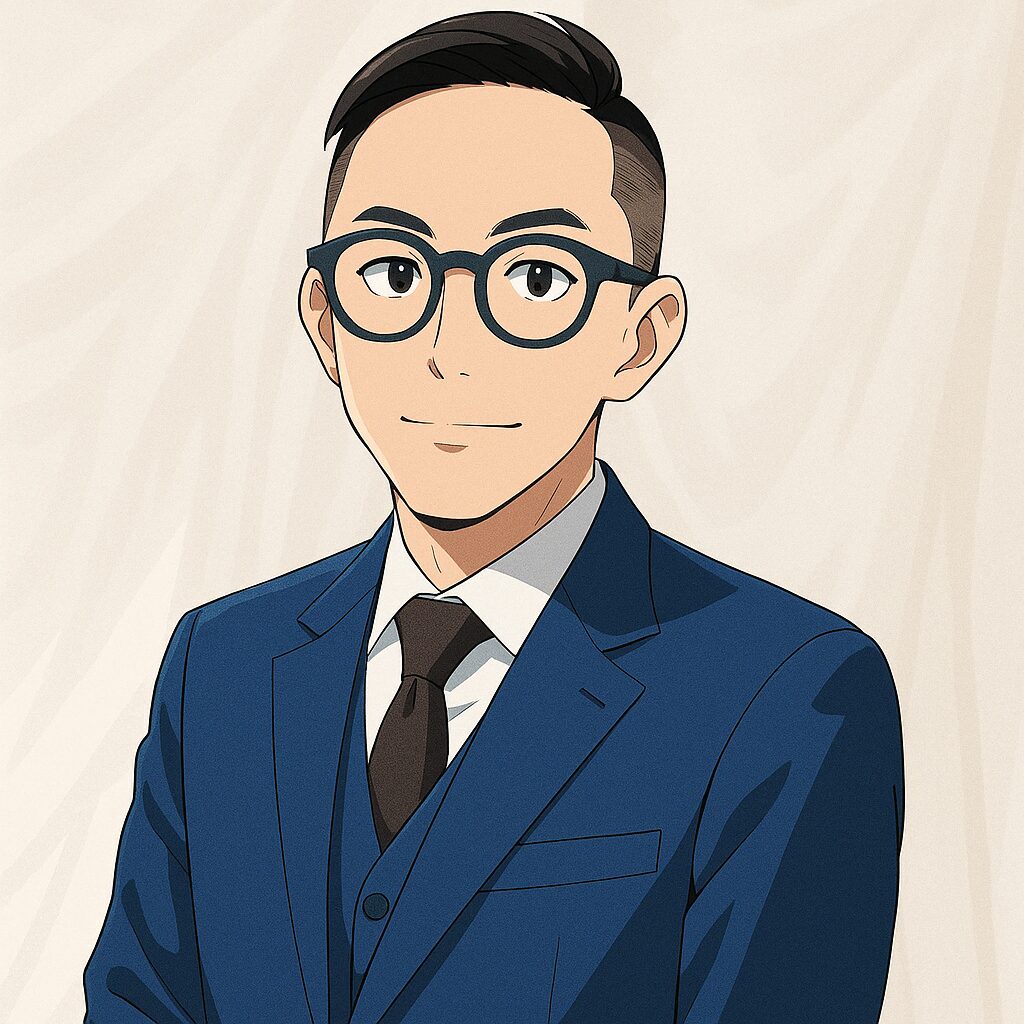
身元保証人を立てられない場合でも申請することは可能です。その場合は、身元保証人が見つからない理由を具体的に説明し、ご自身の収入や預貯金などで十分に生計を維持できることを、より丁寧に立証する必要があります。ただし、許可のハードルは上がる可能性があるので、なるべく見つけるのが好ましいですね。
6-4. Q. 申請中に在留期限が切れてしまう場合は?

申請中に在留期限が切れてしまいそうです。どうすればいいですか?
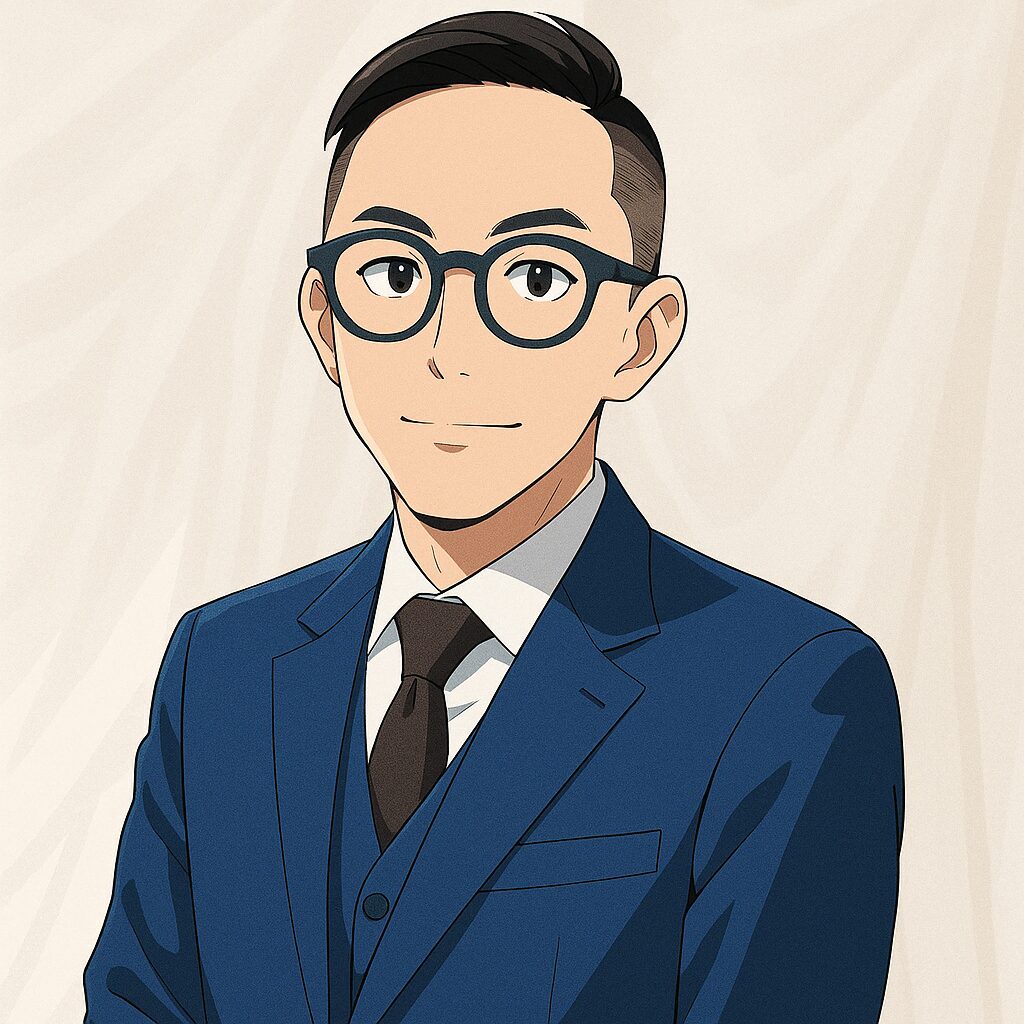
原則として在留期限までに行う必要がありますが、申請が受理されれば、審査結果が出るまでの間(最長で在留期間満了日から2ヶ月を経過する日まで)は、特例として現在の在留資格のまま日本に滞在できます(特例期間)。ただし、特例期間中に出国する場合は「みなし再入国許可」の対象外となるなど注意点があるため、在留期限が近い場合は早めに申請準備を進めましょう。
7. 不安な手続きは専門家へ相談!行政書士に依頼するメリット
ここまで読んで、「やっぱり手続きが複雑そう…」「自分で書類を集めて申請するのは不安…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、在留資格申請の専門家である行政書士に相談・依頼することを検討しましょう。
7-1. メリット1:複雑な書類作成・収集を任せられる
必要書類リストを見て分かる通り、収集・作成すべき書類は多岐にわたります。特に、申請理由書は許可を左右する重要な書類であり、ご自身の状況を的確かつ有利に伝えるための専門的な知識が必要です。行政書士に依頼すれば、これらの煩雑な作業を代行してもらうことができます。
7-2. メリット2:個別の状況に合わせた最適なアドバイス
収入状況、お子様の年齢、身元保証人の有無など、申請者の状況は一人ひとり異なります。行政書士は、あなたの個別の状況を詳しくヒアリングした上で、許可の可能性を高めるための最適なアドバイスや、追加で提出すべき書類などを的確に判断してくれます。
7-3. メリット3:入管とのやり取りを代行してもらえる
申請書類の提出はもちろん、審査期間中に入管から追加書類の提出指示や質問があった場合なども、行政書士があなたに代わって対応します。日本語でのコミュニケーションや専門的な質疑応答に不安がある方にとっては、大きな安心材料となるでしょう。
8. まとめ:離婚後も子供と日本で安心して暮らすために
日本人の方との離婚は、外国人の方にとって大きな転機ですが、お子様がいらっしゃる場合、それは新たなスタートでもあります。お子様と一緒に日本で安心して暮らし続けるためには、離婚後の適切な手続き、特に在留資格の変更が不可欠です。
8-1. 離婚後の手続きの重要性(届出と在留資格変更)
Check Point!
- 離婚後14日以内に入管への届出を忘れずに行いましょう。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格は失効対象となるため、速やかになど他の在留資格への変更申請を行いましょう。
8-2. 「定住者」ビザ取得のポイント再確認
Check Point!
- お子様の親権・監護権を持っていること。
- 日本でお子様を養育していく意思と能力があること。
- 安定した収入・生計維持能力があること(養育費含む)。
- 原則として身元保証人を立てること。
- 必要書類を漏れなく準備し、正直かつ丁寧に申請すること。
8-3. 不安な方は早めに行政書士へご相談ください
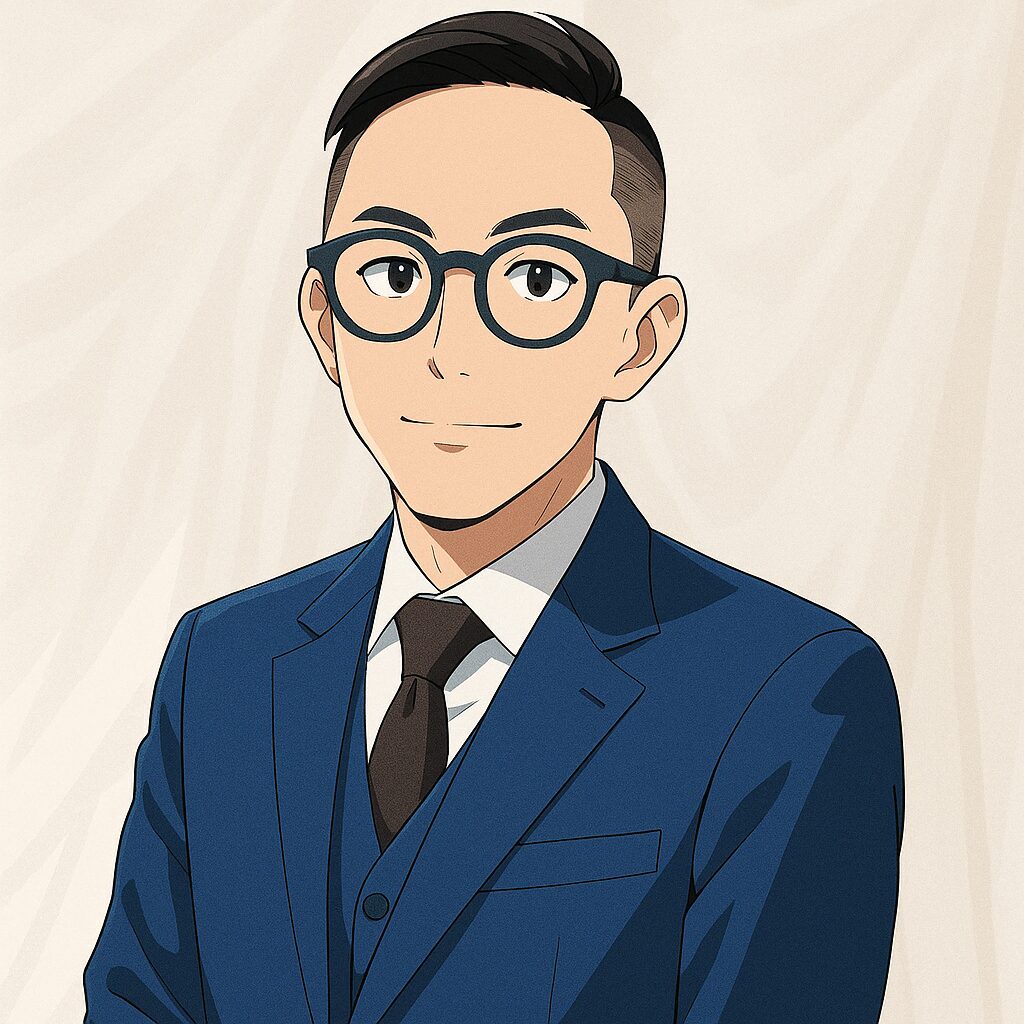
齋藤亮太
いかがだったでしょうか?在留資格の変更手続きは、ご自身の、そして大切なお子様の将来を左右する重要な手続きです。書類の準備や申請手続きにご不安がある方、確実に許可を得たい方は、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で在留資格申請を専門とする行政書士にご相談ください。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、お子様との日本での新しい生活を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの不安が少しでも解消され、お子様と共に安心して日本で暮らせる未来への第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
お問い合わせ・ご相談はこちら
東京都杉並区の行政書士齋藤亮太事務所の代表行政書士。
【在留資格(ビザ申請)】【自動車関連手続き】【補助金申請】など幅広くサポート。
在留ビザ申請についてお困りごとがあればお気軽にご相談ください。
あなたの心配に“心配り”でお応えします!