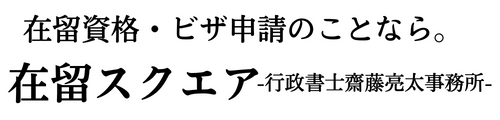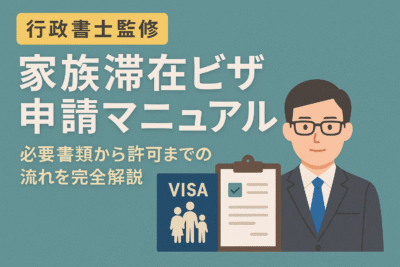在留資格更新セルフ申請ガイド|自分でできるやり方と注意点【失敗しないチェックリスト付】
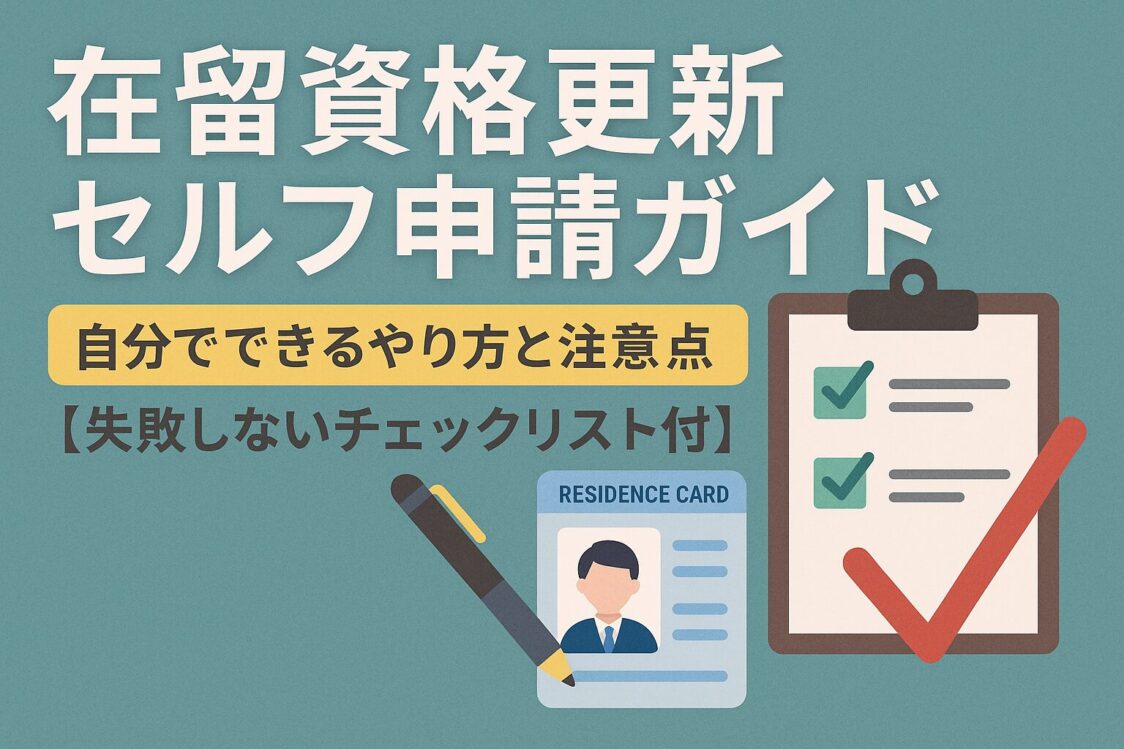
目次
1. 在留資格更新、ご自身での手続きをお考えですか?
1-1. 多くの外国人の方がおこなう「更新手続き」
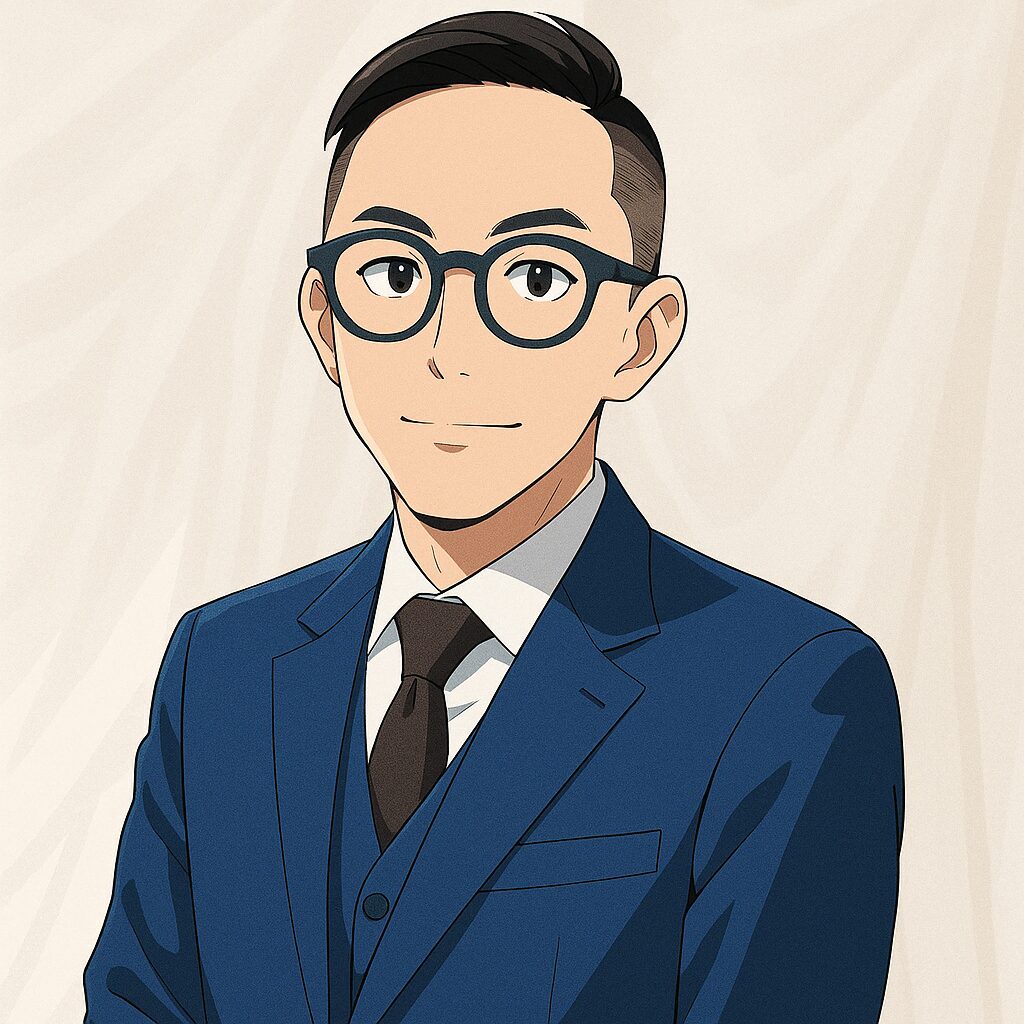
齋藤亮太
こんにちは!行政書士の齋藤亮太です。
この記事をご覧の皆様の中には「在留資格」の更新時期が近づき、ご自身での手続きについて、不安であったり悩まれている方も多いかもしれません。
費用を節約したい、自分のことは自分でしたい、そんな風に考えるのはとても自然なことだと思います。
日本で生活していくために重要な手続きですから、少し緊張するかもしれません。でも、安心してください。手続きの流れや必要書類、注意点をしっかり理解し、丁寧に準備を進めれば、ご自身で更新を完了させることは十分に可能です。
1-2. でも、ちょっと待って!更新手続きに潜む注意点
ただ、ご自身で手続きを進める上では、いくつか注意しておきたいポイントもあります。「書類が少し足りなかった」「書き方が間違っていた」「うっかり申請期限を過ぎてしまった」…そんな小さなミスが、審査に時間がかかったり、最悪の場合、不許可につながってしまう可能性もゼロではありません。 特に、お仕事が変わった、家族が増えた、引っ越しをしたなど、前回の申請時から状況に変化があった場合は、より慎重な準備が求められます。 私たち行政書士は、皆さんのような外国人 方々のビザ(在留資格)申請をサポートする専門家です。もちろん、ご自身でできるのが一番ですが、「ちょっと不安だな」「これはどうすればいいんだろう?」と感じた時に、頼れる存在がいることも知っておいていただけると嬉しいです。この記事では、皆さんが自信を持って更新手続きを進められるよう、専門家の視点から詳しく解説していきます。
1-3. この記事でわかること:自分で更新するための完全ガイド
この記事を最後まで読んでいただければ、以下のことがわかります。
この記事で解説すること
- 在留資格更新の基本的なルール(なぜ、いつまでに必要か)
- 具体的な申請方法のステップ(書類集めから提出まで)
- オンライン申請という選択肢について
- 絶対に揃えるべき書類と、あなたの状況に応じた追加書類の例
- 多くの人が見落としがちな、失敗しないための重要チェックポイント
- 万が一、不許可になったり審査が長引いた場合の対処法
- どんな時に専門家(行政書士)に相談すると良いか
それでは、一緒に在留資格更新について学んでいきましょう!
2. 在留資格の更新とは? 基本的な知識をおさらい
2-1. なぜ在留資格の更新が必要なのか?
皆さんが日本に滞在するためには、パスポートとは別に「在留資格」が必要です。これは、日本で行うことができる活動の種類(仕事、勉強、家族との生活など)と、滞在できる期間(「在留期間」)を定めたものです。 在留カードに記載されている「在留期間の満了日」までに更新手続きを行わないと、その翌日から「オーバーステイ(不法残留)」という状態になってしまいます。オーバーステイは法律違反であり、日本から強制的に退去させられたり、将来的に日本への入国が難しくなったりする、非常に重い結果を招きます。 ですから、日本での生活を続けたい場合は、必ず期限内に在留資格の更新手続きを行う必要があるのです。これは、日本で生活する外国人にとって、最も基本的なルールのひとつと言えるでしょう。
2-2. 更新申請はいつからいつまでに行うべき?
では、いつから更新申請ができるのでしょうか? 原則として、在留期間の満了日を迎える3ヶ月前から申請が可能です。例えば、在留期間の満了日が10月20日であれば、7月20日から申請を受け付けてもらえます。 「まだ3ヶ月もあるから大丈夫」と思っていると、意外と時間は早く過ぎてしまうものです。必要書類を集めたり、申請書を作成したりするには、思った以上に時間がかかることもあります。また、出入国在留管理局(以下、入管)が混雑していて、申請までに時間がかかる場合もあります。 特に重要なのは申請期限です。これは在留期間の満了日当日までです。1日でも遅れると、原則として更新申請は受け付けてもらえず、オーバーステイになってしまいます。 審査自体にも時間がかかります(通常2週間~1ヶ月程度ですが、在留資格や申請時期、状況により異なります)。余裕をもって、できれば満了日の1~2ヶ月前には申請を済ませておくことを強くお勧めします。
関連情報:出入国在留管理庁 - 在留期間更新許可申請 URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
2-3.「許可」と「不許可」:その後の流れの違い
無事に申請が受理されると、入管で審査が行われます。審査の結果「許可」となれば、新しい在留期間が記載された在留カードを受け取ることができ、引き続き日本で生活できます。通常、許可通知のハガキが届き、指定された期間内に入管へ行って手続きをします(収入印紙の購入が必要です)。 一方、残念ながら「不許可」となった場合は、その理由が記載された通知書が交付されます。不許可になると、原則として現在の在留期間満了日までに日本から出国しなければなりません。ただし、不許可の理由によっては、書類を修正して再申請したり、別の在留資格への変更を検討したり、「特定活動」という出国準備のための在留資格に変更申請したりする道が残されている場合もあります。不許可通知を受け取ったら、まずは落ち着いて入管に理由の詳細を確認し、今後の対応を速やかに検討することが重要です。
3.【実践編】在留資格更新の申請方法:ステップ・バイ・ステップ解説
ここからは、実際に自分で在留資格を更新するための具体的なステップを見ていきましょう。
STEP1: 自分の状況に合った必要書類を正確に把握する
更新手続きで最も重要と言っても過言ではないのが、必要書類をもれなく、正確に集めることです。必要書類は、現在の在留資格の種類、日本での活動内容(どんな仕事をしているか、どこの学校に通っているかなど)、そして個々の状況によって異なります。 まずは、出入国在留管理庁のウェブサイトで、ご自身の在留資格に対応する「在留期間更新許可申請」のページを確認しましょう。「提出書類」のリストが掲載されています。 注意点として、ウェブサイトに載っているのはあくまで一般的なリストです。審査官が個別の状況に応じて、リストにない書類の提出を追加で求めることもあります。例えば、転職したばかりの場合や、収入に変化があった場合などは、それを説明するための補足資料が必要になることが多いです。 「自分の場合は、どの書類が必要なんだろう?」と迷ったら、ウェブサイトをよく読んだり、入管のインフォメーションセンターに問い合わせたりして、確実に把握することが最初のステップです。
STEP2: 申請書を作成する際の注意点
必要書類の中心となるのが「在留期間更新許可申請書」です。この様式は、入管の窓口でもらうか、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。(Excel形式やPDF形式があります) 申請書を作成する際は、以下の点に注意してください。
- 正確に記入する: 氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、在留カード番号などは、お持ちの書類と一字一句同じように正確に書いてください。
- 正直に書く: 事実と異なることを書くのは絶対にやめましょう。虚偽申請と判断されると、更新が不許可になるだけでなく、今後の在留資格申請にも大きな影響が出ます。
- 空欄を作らない: 該当しない項目以外は、基本的に全ての欄を埋めるようにしましょう。もし書き方が分からない項目があれば、そのままにせず、入管に問い合わせるか、専門家に相談しましょう。
- 変更点は明確に: 前回の申請時から所属機関(会社や学校)が変わった、役職が変わった、家族構成が変わったなど、変更があった場合は、その内容を正確に記載する必要があります。
- 署名: 最後に申請者本人が署名することを忘れないでください。 申請書は、審査官があなたの状況を把握するための最も基本的な書類です。時間をかけて、丁寧に作成しましょう。 関連情報: 出入国在留管理庁 - 各種申請書様式(在留期間更新許可申請) URL: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html (申請書ダウンロードへのリンクも含む)
STEP3: 地方出入国在留管理局へ申請書類を提出する
書類がすべて揃ったら、あなたの住所地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局、出張所)の窓口へ提出に行きます。
<窓口申請の流れ(一般的な例)>
- 受付: 庁舎に到着したら、案内表示に従って在留資格更新の担当窓口へ向かいます。多くの場合、番号札を取って待つことになります。
- 待機: 混雑状況によっては、数時間待つこともあります。時間に余裕を持って行きましょう。
- 申請: 番号が呼ばれたら窓口へ行き、準備した書類一式を提出します。
- 書類チェック・質疑応答: 窓口の担当官が書類を確認します。その場で簡単な質問(仕事内容の確認など)をされることもあります。
- 受理: 書類に不備がなければ申請は受理され、「申請受付票」のような控えが渡されます。この控えは、結果を受け取るまで大切に保管してください。
ワンポイントアドバイス
最近では、おおよそどの入管でも事前予約ができますので、予約しておくほうがスムーズにいくでしょう。以下は、東京入管の予約システムです。
関連情報:東京出入国在留管理局申請予約システム URL:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/shinsei_yoyaku.html
<持参するもの>
- 準備した申請書類一式
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
現在は、後述するオンライン申請も利用可能になっています。ただし、利用には条件があるため、ご自身で利用できるか事前に確認が必要です。
4. 便利?それとも注意が必要?在留申請のオンラインシステム
4-1. オンライン申請のメリット・デメリット
数年前から「在留申請オンラインシステム」が導入され、一部の在留資格更新手続きなどがインターネット経由で行えるようになりました。
<メリット>
- 入管の窓口へ行く必要がない(交通費や時間の節約)
- 24時間いつでも申請が可能(土日祝日含む)
- 窓口での長い待ち時間がない
<デメリット>
- 利用するためには事前の利用者情報登録が必要
- マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタ、対応するPC環境が必要
- システムの操作に慣れが必要
- 全ての在留資格・申請者が対象ではない
- 利用するための準備や条件を理解しておくことが必要
4-2. 誰が利用できる?オンライン申請の対象者
オンライン申請を利用できるのは、以下のような方々です。
- 申請者本人: マイナンバーカードを持っていること、など一定の条件を満たす場合。
- 申請取次者: 弁護士や行政書士など、入管への申請取次資格を持つ専門家。
- 所属機関の職員: 申請者本人が所属する企業や学校の職員で、地方出入国在留管理局長から承認・届出がされた者。 ご自身(申請者本人)でオンライン申請を行いたい場合は、まずマイナンバーカードを取得し、その後、在留申請オンラインシステムへの利用者情報登録を行う必要があります。
関連情報: 出入国在留管理庁 - 在留申請のオンライン手続 URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
4-3. オンライン申請を利用するための準備
ご自身でオンライン申請を行う場合、主に以下のものが必要です。
- 有効なマイナンバーカード
- マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ(家電量販店などで購入可能)
- インターネットに接続されたパソコン(OSやブラウザのバージョンに指定がある場合があります)
- 在留申請オンラインシステムへの利用者情報登録(事前にIDとパスワードを取得)
- 提出する書類のデータ(PDF形式など) 準備に少し手間がかかるかもしれませんが、一度環境を整えれば、次回以降の申請がスムーズになる可能性があります。
5.【チェックリスト付】在留資格更新に必要な書類一覧
ここでは、在留資格更新に必要な書類について、もう少し詳しく見ていきましょう。ただし、これはあくまで一般的な例です。あなたの状況に合わせた正確な必要書類は、必ず最新の出入国在留管理庁ウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。
5-1. 全ての申請者に共通する必要最低限の書類
以下の書類は、基本的にどの在留資格の更新申請でも必要となります。
- □ 在留期間更新許可申請書: 1通(様式は入管HPからダウンロード)
- □ 写真: 1葉(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影、無帽、無背景、鮮明なもの)※申請書に貼付
- □ パスポートの提示
- □ 在留カードの提示
5-2.【在留資格別】主に必要となる追加書類の例
上記に加えて、在留資格の種類や活動内容に応じて以下のような書類が必要になることが一般的です。
【技術・人文知識・国際業務、技能など(就労ビザ)の場合】
- □ 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分、または最新年度分)
- □ 所属機関(会社)の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)又はそれに代わる書類
- □ 雇用理由書、職務内容を説明する資料(転職した場合など)
- □ 会社の登記事項証明書(必要な場合)
【経営・管理の場合】
- □ 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分、または最新年度分)
- □ 所属機関(会社)の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)又はそれに代わる書類
- □ 直近年度の決算報告書の写し
- □ 事業内容を明らかにする資料
【留学の場合】
- □ 在学証明書
- □ 成績証明書
- □ 学費等の支弁能力を証明する書類(奨学金証明、送金証明、預金残高証明など)
- □ (資格外活動許可を受けている場合)資格外活動の内容・時間・報酬を証明する書類
【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の場合】
- □ 配偶者(日本人・永주者)の戸籍謄本または住民票
- □ 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分、または最新年度分)
- □ 身元保証書(配偶者が身元保証人になる場合が多い)
- □ 質問書(生活状況などを記載) これはほんの一例です。特に、転職した、独立した、家族が増えた・減った、などの変化があった場合は、上記以外の書類も必要になる可能性があります。
5-3. 書類準備で失敗しないために
書類集めは大変ですが、ここで手を抜くと後で困ることになります。以下の点をチェックしましょう。
- □ 有効期限は大丈夫?:パスポートや在留カードはもちろん、提出する証明書類(住民票、納税証明書など)は、通常、発行日から3ヶ月以内のものが求められます。古い書類は使えません。
- □ コピーは鮮明?:原本ではなくコピーを提出する書類もありますが、文字が潰れて読めないような不鮮明なコピーはNGです。
- □ 翻訳は必要?:外国語で書かれた書類(本国の結婚証明書など)には、基本的に日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳者名と連絡先を記載するのが一般的です。
- □ 全ての書類が揃っていますか?:提出前に、リストと照らし合わせて、全ての書類が揃っているか、何度も確認しましょう。
- □ 書類の内容は整合性が取れていますか?:申請書の内容と、提出する証明書類の内容(住所、勤務先、収入など)が一致しているか確認しましょう。
6. 自分で更新する際の重要注意点!失敗しないための7つのポイント
在留資格の更新を自分で手続きする際に、特に注意してほしいポイントを7つにまとめました。
これらは、不許可になってしまうケースでよく見られる原因でもあります。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせてチェックしてみてください。
注意すべき7つのポイント
- ポイント1:申請期間は絶対に厳守!
何度も繰り返しますが、これが最も重要です。在留期間の満了日までに必ず申請を完了させてください。1日でも遅れるとオーバーステイとなり、更新は原則できません。「うっかり忘れていた」では済まされない、非常に厳しいルールです。カレンダーに印をつける、スマートフォンのリマインダーを設定するなど、絶対に忘れない工夫をしましょう。 - ポイント2:提出書類に不備・不足はないか?
書類が足りなかったり内容に誤りがあったりすると、入管から追加の書類提出を求められることもあり、審査が大幅に遅れる原因になります。最悪の場合、必要な情報が確認できないとして不許可になる可能性もあります。提出前には、入念なチェックを怠らないでください。可能であれば、ご家族や信頼できる友人など、第三者の目でも確認してもらうと良いでしょう。 - ポイント3:申請内容と実際の活動・生活状況は一致しているか?
申請書に書いた内容と、あなたの実際の活動(仕事の内容、学校での状況など)や生活状況(収入、同居家族など)が一致していることは大前提です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているのに、申請書に書いた専門的な業務とは全く関係のない単純作業ばかりしている、といった場合は、在留資格に合った活動をしていないと判断され、更新が認められない可能性があります。
転職や引っ越しなど、生活に変化があった場合は、正直に、正確に申告することが重要です。 - ポイント4:税金や社会保険料の未納はないか?
住民税や国民健康保険料、年金などをきちんと納めているかは、日本で安定した生活を送る上での重要な要素であり、在留資格の審査においても非常に重視されます。特に永住許可申請では必須ですが、通常の更新申請でもチェックされるポイントです。「少しくらいなら大丈夫だろう」という甘い考えは禁物です。もし未納がある場合は、更新申請の前に必ず納付し、その証明書(納税証明書など)を提出できるようにしておきましょう。 - ポイント5:収入要件はクリアしているか?
特に、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営・管理」などの在留資格では、日本で独立して安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかが厳しく審査されます。「留学」の場合も、学費や生活費をきちんと支払える能力(経費支弁能力)の証明が必要です。収入が不安定だったり、極端に少なかったりすると、更新が認められない場合があります。課税証明書、納税証明書、預金残高証明書、給与明細などで、安定した収入があることを客観的に示す必要があります。 - ポイント6:法律違反(交通違反含む)はないか?
日本で法律を守って生活していること(素行善良要件)も、在留資格の更新において大切な要素です。逮捕歴や犯罪歴がある場合はもちろんですが、意外と見落としがちなのが交通違反です。駐車違反や速度超過など、比較的軽微な違反であっても、何度も繰り返していると「法令遵守の意識が低い」と判断され、審査に不利に働く可能性があります。日頃から日本のルールを守って生活することが大切です。 - ポイント7:前回の申請内容との整合性
入管は、過去の申請記録を保管しています。今回の申請内容が、過去に提出した書類の内容(学歴、職歴、家族構成など)と矛盾していると、「どちらかが嘘なのではないか?」と疑念を持たれてしまいます。もし、前回の申請内容に誤りがあった場合などは、正直にその旨を説明する必要があります。意図的な虚偽でなくとも、矛盾点は審査官に不信感を与えかねません。可能であれば、前回の申請書類の控えを確認し、整合性をチェックしましょう。
7. もしもの時:更新申請が不許可になったら?審査が長引いたら?
どんなに注意深く準備しても、予期せぬ事態が起こる可能性はあります。ここでは、更新申請がうまくいかなかった場合の対応について説明します。
7-1. 不許可通知を受け取った場合の対応
もし「不許可」の通知が届いたら、まずは落ち着いてください。パニックにならず、通知書の内容をよく読みましょう。そして、できるだけ早く、申請した入管の窓口へ行き、不許可になった理由を具体的に確認することが重要です。理由を聞くことで、何が問題だったのか、再申請の可能性があるのか、別の手続きが必要なのかが見えてきます。 理由によっては、問題点を修正して再申請できる場合もありますし、現在の在留資格での更新は難しいと判断された場合は、別の在留資格(例:就労ビザがダメなら、日本人配偶者ビザへ変更など)への変更申請を検討する必要があるかもしれません。あるいは、残念ながら日本を出国しなければならないケースもあります。 不許可理由はケースバイケースですので、必ずご自身の状況に合わせて、入管の担当官や私たちのような行政書士に相談することをお勧めします。一人で悩まず、早めに行動することが大切です。
7-2. 審査期間はどれくらい?結果がなかなか来ない場合
在留資格更新の標準的な審査期間は、在留資格により異なりますが通常2週間から1ヶ月程度です。しかし、これはあくまで目安です。申請内容が複雑だったり、書類に不備があって追加提出が必要になったり、申請者が多い時期(例:3月~4月など)だったりすると、審査に2ヶ月、3ヶ月以上かかることも珍しくありません。 心配なのは、審査中に在留期間の満了日が来てしまうケースですが、期限内に更新申請が受理されていれば、結果が出るまでの間、または申請日から2ヶ月間のどちらか短い期間は、特例として引き続き日本に滞在することが認められています。 この期間中は、在留カードの裏面に「申請中」のスタンプが押されます(またはシールが貼られます)。 とはいえ、あまりにも結果通知が遅い場合は、一度入管に審査状況を問い合わせてみるのも良いでしょう。その際、申請時に受け取った「申請受付票」に記載されている申請番号を伝えるとスムーズです。
関連情報:出入国在留管理庁- 在留審査処理期間 URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001435769.pdf
7-3. 不安な時は早めに相談を
不許可になった場合や、審査が長引いて「どうなっているんだろう?」「このままで大丈夫かな?」と不安になった時は、一人で抱え込まないでください。 まずは、出入国在留管理庁が開設している「外国人在留総合インフォメーションセンター」に電話などで相談してみるのも一つの方法です。多言語に対応しており、一般的な手続きについて教えてもらえます。
関連情報: 出入国在留管理庁 - 外国人在留総合インフォメーションセンター URL: https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
8.「やっぱり不安…」「手続きが複雑…」そんな時は行政書士にお任せ!
ここまで、ご自身で在留資格を更新する方法と注意点を詳しく解説してきました。「なるほど、意外とやることが多いな」「自分でできるか、ちょっと自信がなくなってきた…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、無理せず行政書士に頼ることも考えてみてください。
8-1. 行政書士に依頼するメリットとは?
私たち行政書士に在留資格の更新手続きを依頼すると、以下のようなメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
- 適切な書類作成: あなたの状況に合わせた適切な申請書類を作成しますので、書類不備のリスクを減らせます。
- 時間と労力の節約: 面倒な書類集めや申請書の作成、入管への申請手続き(申請取次)を代理でおこなってくれるので、仕事や学業、家庭生活に集中することができます。
- 許可率向上: 個々のケースに応じた適切な提出な資料・書類の選択により許可の可能性を高めます。
- 不測の事態への対応: 追加書類を求められたり、審査が難航したりした場合でも、適切に対応し最後までサポートします。
- 精神的な安心感: 一人で手続きを行うことによる不安やストレスから解放され、安心して結果を待つことができます。
8-2. こんな方は行政書士への相談がおすすめ!
特に、以下のような状況に当てはまる方は、一度、行政書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
- 自分で書類を集めたり、申請書を書いたりするのが苦手、または不安が大きい方
- 過去に在留資格申請で不許可になった経験がある方
- 転職したばかり、会社を設立した、家族構成が変わったなど、状況が複雑な方
- 日本語での書類作成や、入管での説明に自信がない方
- 仕事や学業が忙しくて、手続きに時間を割くのが難しい方
- 確実に更新許可を得たい、少しでも不許可のリスクを減らしたい方
- オンライン申請を利用したいが、自分で準備するのが難しいと感じる方
9. まとめ:在留資格更新をスムーズに進めるための最終チェック
9-1. 自分で更新手続きを行う方へ:最も大切なこと
ご自身で在留資格の更新に挑戦するあなたへ。最も大切なのは、「早めの準備」「正確な情報収集」「丁寧な書類作成」「正直な申告」そして「期限厳守」です。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを着実にこなしていけば、必ず道は開けます。自信を持って、でも油断せずに、取り組んでください。
9-2. 困った時、迷った時の相談先
手続きを進める中で、分からないことや不安なことが出てくるのは当然です。そんな時は、一人で悩まずに、以下の相談先を活用しましょう。
- 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター: 一般的な手続きに関する質問に答えてくれます。
- 申請取次を持つ弁護士や行政書士: あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスや、手続きの代行をサポートしてくれる心強い存在となるでしょう。
9-3. 最終確認!重要ポイントチェックリスト
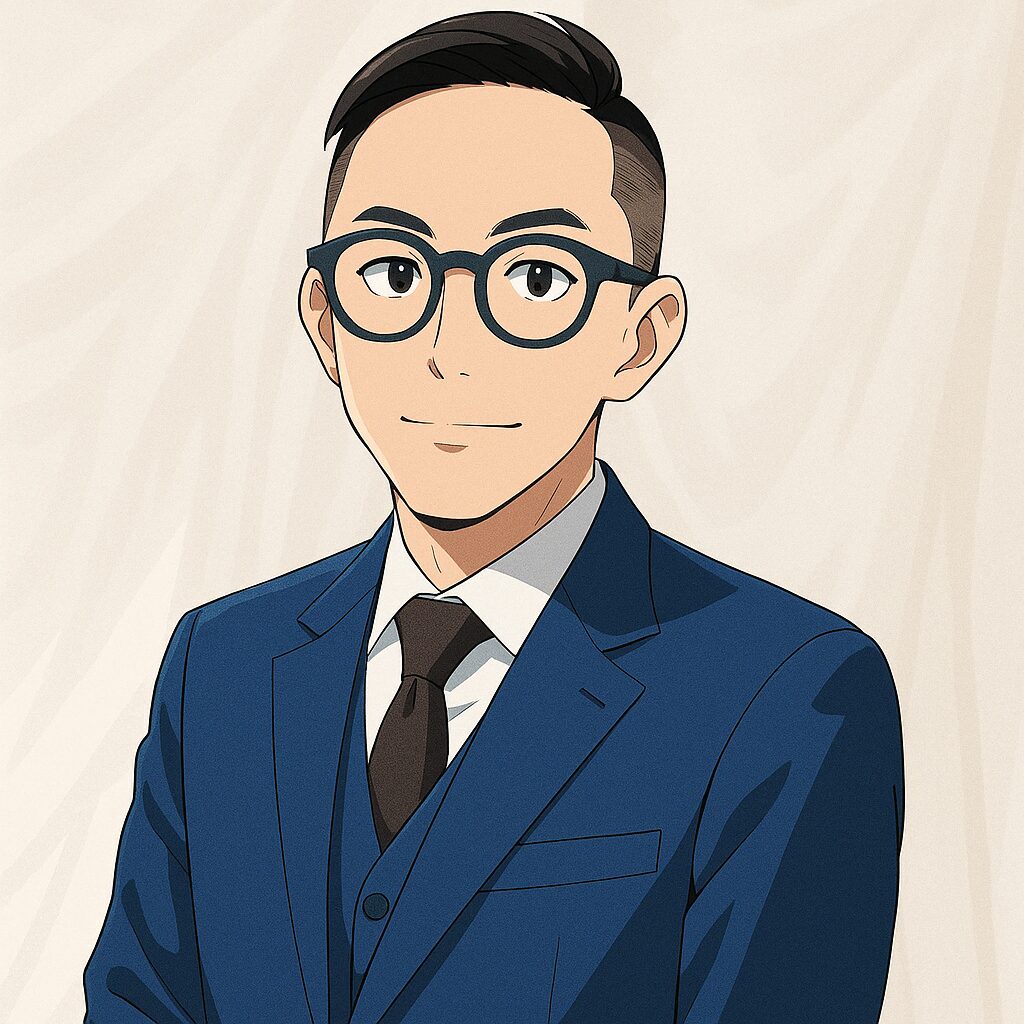
齋藤亮太
いかがだったでしょうか?申請書類を提出する前に、あらためて以下の点をチェックしましょう!
CheckPoint!
- □ 申請期間は大丈夫?(満了日の3ヶ月前~満了日当日まで)
- □ 必要な書類は全て揃っている?(入管HPで要確認!)
- □ 書類の有効期限(発行日)は大丈夫?(通常3ヶ月以内)
- □ 申請書の内容は正確?正直?(パスポート等と一致)
- □ 前回の申請内容と矛盾はない?
- □ 実際の活動・生活状況と申請内容は一致している?
- □ 税金や社会保険料の未納はない?
- □ 収入は安定していることを証明できる?(必要な場合)
- □ 法律違反(交通違反含む)はない?
- □ 写真の規格は合っている?
- □ パスポート、在留カードの原本提示を忘れない!
この記事が、皆さんの在留資格更新手続きの一助となれば幸いです。日本での充実した毎日が、これからも続くことを心から願っています。
もし、手続きに関してご不明な点やご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談はこちら
東京都杉並区の行政書士齋藤亮太事務所の代表行政書士。
【在留資格(ビザ申請)】【自動車関連手続き】【補助金申請】など幅広くサポート。
在留ビザ申請についてお困りごとがあればお気軽にご相談ください。
あなたの心配に“心配り”でお応えします!